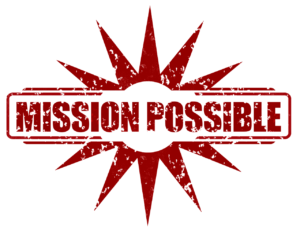4月5日にJMRXとの共同開催で、マーケティングアプリケーションズ様の会場で、英国のThe Market Research Societyのウェビナー:「Neuro Design – Aestheticsの心理学」(Darren Bridger氏のプレゼンテーションビデオ)を見た後、日本でのニューロデザインについて、2グループに分かれてディスカッションを行いました。

ニューロデザインとは
Neuro Design(ニューロデザイン)は、比較的新しい分野で、心理科学的に、人がどのようなデザインにどのように反応するかを調べ、効果的なデザイン作成に活用されています。
VUCA、すなわちVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、 Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の時代において、デザインはますます重要になってきています。

ディスカッションのアウトプット
1. 日本でのNeuro Designはどの程度進んでいるのか
一言で言えば、日本ではニューロデザインはあまり進んでないという意見でした。その理由として、主に以下の点が挙げられていました。
- 紙面やウェブデザインには有効。脳波やMRIは医療では一般的。その他の分野では、リサーチした後にアクションにつなげるのが難しい。
- アイトラッキングは一般的。
- ニューロデザインのリサーチをしても、なぜ人が反応しているのか、わからない。結局、後でインタビューしている。
- 情報量が多すぎて判定しにくい。
2. 日本でNeuro Design & Aesthetics(美的、審美的)リサーチを行う課題
日本でニューロデザインに関するリサーチを行う上で、様々な課題が挙げられました。主に挙げられたのは、以下の課題です。
- 日本人の表情が乏しい。(顔の表情から感情分析を行うケースなど)
- 日本はニューロだけになることが多いが、海外はニューロデザインプラスアルファのリサーチ分析がある。
- 安くて手軽な機材はやはり使えない。
- 倫理的な観点でハードルが高い。
- 日本では精度を求めすぎている。
3. 日本だからこそできるニューロデザインとAestheticsのリサーチ
日本でニューロデザインに関する課題は多く挙げられましたが、ディスカッションは課題提議だけには終わりませんでした。参加者の方々からは、「日本だからこそ」という解決案も出されました。
- 日本人は、深読みするハイコンテクストな国民性。日本人はリアクションが薄いので、その深さはニューロで解決できるかもしれない。
- ニューロの反応と言葉の解釈が繋げられると使えるのではないか。
- ニューロは、基礎データとして使える。脳の反応は変わらないから。
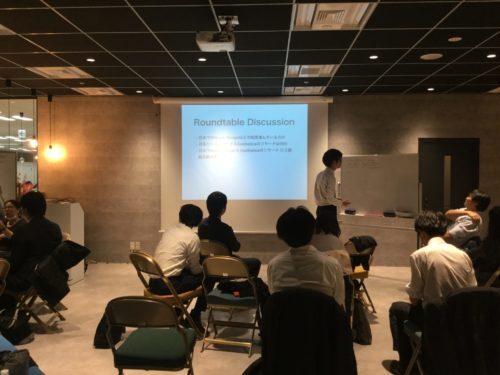
ご参加頂きました皆様、誠にありがとうございました!